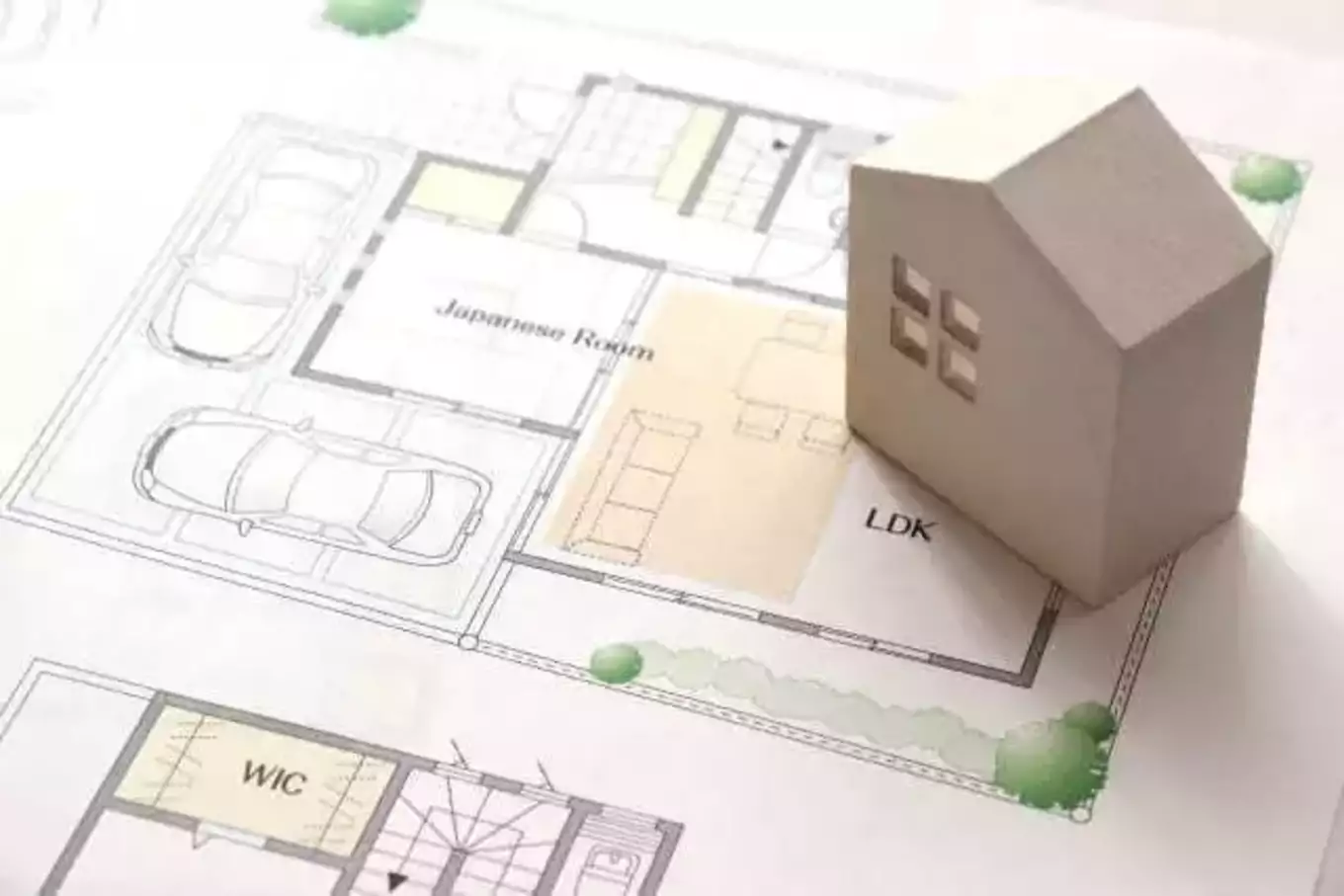建築の基本!建ぺい率と容積率とは

建ぺい率
建ぺい率とは、土地(敷地)を真上から見たとき、土地面積に対して建築可能な面積の割合です。建ぺい率60%とある場合は、その土地の60%までの面積に建物の建築が可能に。「建築面積÷敷地面積×100」で求められます。
二階が一階よりも大きい場合は、二階の面積が建ぺい率計算の対象となるため、真上から土地を見る必要性があるのです。
そんな建ぺい率は建築基準法第53条により、次の3つのケースでは、設定されている割合より10%増で建てられる場合があります。
防火地域に耐火構造の家を建てる
建物が密集している場所で火災が発生すると次々と燃え移り、膨大な被害が懸念されます。そこで被害抑制を目的とした防火地域が設定されており、一定条件の建物以外は不燃材料を使用して家を建てなければなりません。このほかに、一つの土地に複数の建物を建てる場合は耐火構造以外の建物は建てられないなどの条件が付きます。
角地に家を建てる
特定行政庁指定の角地の場合、角地緩和の対象となり建ぺい率がアップします。対象となる角地の条件として、次のような項目があります。
・街区の角にあり、道路の交差点に面している
・土地の両側が道路に面している(角地扱いとなる)
・公園や広場、河川などに面している(角地同等となる)
特定行政庁により緩和条件の詳細が異なるため、気になる土地が建ぺい率緩和の対象であるか分からない場合は、大分市の開発建築指導課に確認を取りましょう。
・街区の角にあり、道路の交差点に面している
・土地の両側が道路に面している(角地扱いとなる)
・公園や広場、河川などに面している(角地同等となる)
特定行政庁により緩和条件の詳細が異なるため、気になる土地が建ぺい率緩和の対象であるか分からない場合は、大分市の開発建築指導課に確認を取りましょう。
容積率
容積率とは、敷地面積に対する建物の延べ床面積の割合です。分かりやすく言えば、「敷地面積に対してどこまで空間を使用できるか」ということになり、容積率は「総床面積÷敷地面積×100」で求められます。
例えば、建ぺい率が50%で容積率100%の100㎡の土地の場合、床面積50㎡ずつの二階建てが建築可能に。また、容積率には次のように対象外となるスペースがあります。
吹き抜け部分
吹き抜け部分は床がないため、容積率を計算するうえで床面積には含まれません。ただし、渡り廊下やキャットウォークのような動物専用の通路や、収納棚の高さが吹き抜けにかかる場合は床面積に該当する可能性があるので注意しましょう。
ベランダ・バルコニー・ひさし(庇)
ベランダをはじめとする建物から突出した部分は、外壁から1m以内であれば容積率として認められません。同じく出窓も次の条件を満たしていれば容積率に該当しないため、覚えておくと良いでしょう。
・床から出窓の下端まで30cm以上ある
・外壁から50cm以内に収まっている
・出窓部分の半分以上が窓である
・床から出窓の下端まで30cm以上ある
・外壁から50cm以内に収まっている
・出窓部分の半分以上が窓である
車庫やガレージ
1/5までという限度はありますが、車庫やガレージも床面積に含みません。
ロフトや屋根裏の収納
車庫やガレージ同様限度はありますが、設置する階の床面積に対し1/2までの大きさのロフトであれば床面積に含まれません。屋根裏には140cmまでの高さ制限があり、それを超えると床面積としてカウントされます。
建ぺい率や容積率は用途地域で異なる

用途地域は都市計画法を基準に、環境保全や利便性向上などに該当する区域が対象となっており、商業系、住居系、工場系の3つに分類されます。
大分市の用途地域を調べる方法
大分市の都市計画区域や用途地域は、大分市役所にある都市計画課の窓口の閲覧図面で確認できます。このほかに、大分市のホームページにある地図情報「おおいたマップ」を活用すると便利です。
参考:「用途地域や都市計画区域の確認について」
参考:「おおいたマップ」
参考:「用途地域や都市計画区域の確認について」
参考:「おおいたマップ」
大分市の住居系用途地域をじっくり解説

第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域は建物の高さが10m~12mまでの制限があり、閑静な住宅エリアです。2階建ての戸建てを中心に、マンションも3階建てくらいまでの高さしか建てられません。また、店舗兼住宅や事務所などを建てたい場合は床面積が50㎡以下という制限があります。また、このエリアに小中学校や診療所などが建築可能で、これらの施設は床面積の制限がないことが特徴です。
大分市では光吉台団地や寒田北団地、星和台団地などが該当します。
第二種低層住居専用地域
建物の高さ制限は第一種低層住居専用地域と一緒ですが、床面積が150㎡以内の店舗が建築可能なため、小規模な飲食店やコンビニなどが建てられます。大分市では、花の木団地や桃園団地、久保山団地などが該当します。
第一種中高層住居専用地域
低層専用地域よりも規模が大きい建物が建築可能で、高等専門学校や大学、病院などが建てられます。店舗に関しても2階以下・床面積が500㎡までと条件が緩和しているため、飲食店やスーパーなどが見られます。
住居専用のためオフィスビルは建てられませんが、集合住宅や2階~3階建ての戸建て、店舗などが混在しており活気があるエリアです。大分市では鶴崎コスモス団地や二目川団地、くすのき坂などが該当します。
第二種中高層住居専用地域
住みやすい環境を意識するなかでも利便性の高い施設が建築可能なエリアで、2階以下・床面積1,500㎡までの各種店舗や事務所が建てられます。大分市では高松や日吉、花津留などが該当し、住まいと仕事場がより近く感じられます。
第一種住居地域
戸建ても建築可能ですが、大規模なマンションや事務所、床面積3,000㎡までのホテルや旅館、スポーツ施設なども建てられるエリアです。あくまでも住居系の用途地域のため、パチンコ店やカラオケボックスなどの建築は禁止されており、大分市では大津町や新川町、勢家などが該当します。
第二種住居地域
第一種住居地域よりも条件が緩和されているエリアのため、パチンコ店やカラオケボックスが建築可能です。また、大規模なホテルや商業施設も建てられますが、住居系の用途地域のため建てる際は周辺の環境に配慮する必要があります。大分市では、田室町や古国府木上線、上野丘南大分線などが該当します。
準住居地域
道路の沿道に建築可能で、住居系の用途地域で最も許容範囲が広いエリアです。駐車場や床面積150㎡以下の自動車に関連する施設が建てられます。このほかに、床面積が200㎡までの小規模の劇場や映画館も建築の対象で、大分市では下郡北や庄野原佐野線、大州浜などが該当します。
田園住居地域
低層住宅と田畑をはじめとする農業用地との調和を目的としたエリアで、建物の建築条件は第一種低層住居専用地域に似ています。大きな違いは店舗兼住宅にあり、店舗部分の床面積500㎡以下の農産物直売所や農家レストランといった農業に関連する店舗や飲食店が建築可能です。田園住居地域は2018年に追加された地域のため、おおいたマップには現在表示されていません。
田園住居地域の土地を購入したい場合は、大分市の都市・まちづくり推進課に確認してみましょう。
>>大分市の土地価格相場・価格の推移について詳しくはこちら!
>>大分市の街並みと公園をチェック!地域の特性を活かした家づくりとは
>>大分市の土地価格相場・価格の推移について詳しくはこちら!
>>大分市の街並みと公園をチェック!地域の特性を活かした家づくりとは
商業系住居地域

近隣商業地域
スーパーや商店街などがあり、住居系用途地域よりも店舗と住居の関係がより密接にあるエリアです。日用品を購入するのに便利な一方、床面積が150㎡までなら工場も建てられるので、土地を購入する場合は周囲の環境をしっかり確認しましょう。大分市では今津留や顕徳町、中島などが該当します。
商業地域
住居よりも商業施設に重きを置いているエリアで、市の中心部や主要駅周辺などに指定されています。銀行やオフィスなども建築可能で、マンションが多く戸建ては少ない傾向です。大分市では大分駅前やパークプレイス大分、あけのアクロスタウン辺りが該当します。
工業系地域

準工業地域
環境に悪影響をもたらす恐れのある工業は対象外のエリアで、住居や店舗、工場が混在している傾向にあります。そのため騒音や火災の危険性などに配慮し、一定の業種の建物は建てられません。住居や工場以外では、病院や教育に関連する施設も建築可能で、大分市では、王子港町や西新地、三佐などが該当します。
工業地域
住居の建築は可能ですが、主に工場が多いエリアです。病院や教育に関連する施設は建てられず、準工業地域では建てられない騒音をはじめとする公害が発生する恐れのある業種も建築可能のため、トラックなどの交通量が多いことも特徴です。大分市では小中島や豊海などが該当します。
工業専用地域
工業専用地域のため大規模な工場やコンビナートが多くあり、工業の妨げとなる建物の建築が原則禁止されているエリアです。大分市では中ノ洲や西ノ洲、青崎などが該当します。
建ぺい率や土地購入で分からないことがあればR+house大分西へ!
土地を探すうえで、土地ごとに設定されている建ぺい率と容積率、用途地域の確認は欠かせません。建物の大きさに制限があるからこそ、緩和条件や床面積の対象外となる範囲を知り、理想的な家を建てましょう。用途地域ごとのエリア紹介をしましたが、詳しくは大分市が運営するおおいたマップをご覧ください。探すのが難しい、気になることがある場合はぜひR+house大分西へご相談ください。
>>理想の家づくりを土地探しからサポートする「R+house」について詳しくはこちら!
>>理想の家づくりを土地探しからサポートする「R+house」について詳しくはこちら!